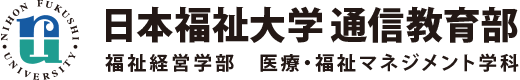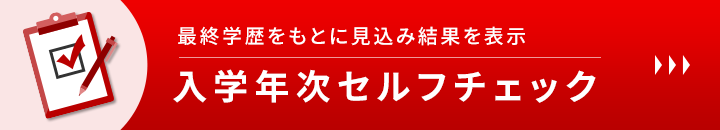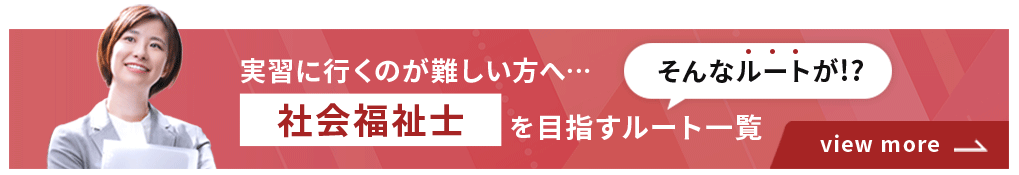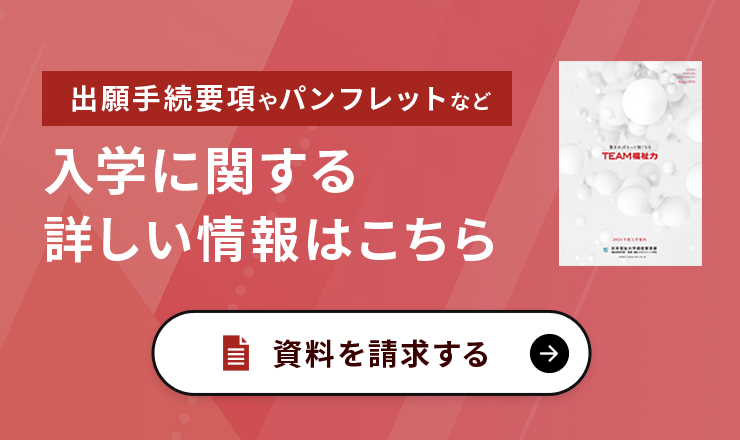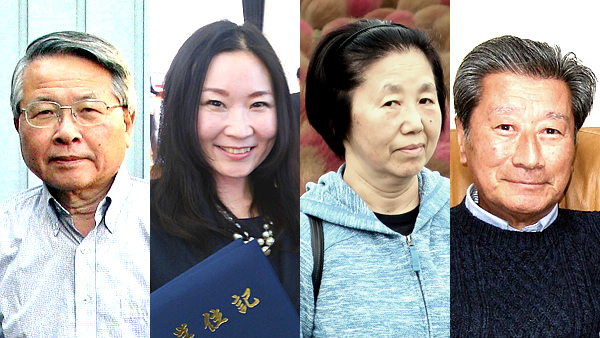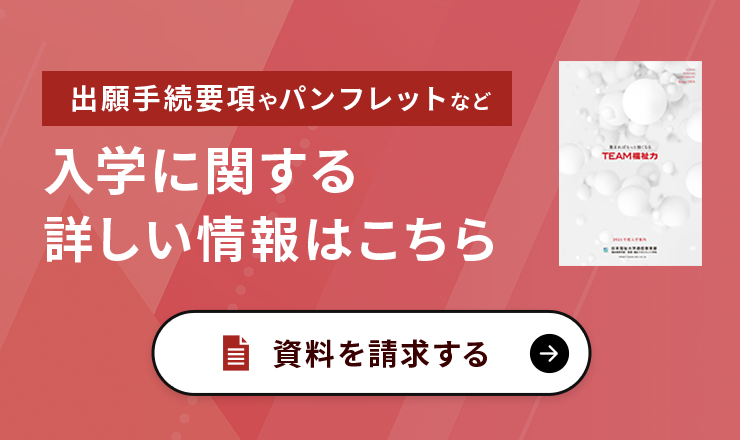ここからページの内容です
社会福祉士 国家試験受験資格
社会福祉士とは
社会福祉士は、介護福祉士とともに、わが国で初めて誕生した社会福祉専門職の国家資格です。
担う役割は、「社会福祉士及び介護福祉士法」に定められており、主として、高齢者や障害者など、福祉ニーズをもつ者に対する
相談援助を業とします。彼らのニーズを受容し、彼らの利益と権利を護るとともに、自立(自律)支援のため、
他の福祉サービス関係者等と連携しながら専門職としての知識・技術を駆使する
社会福祉援助(ソーシャルワーク)の実践を展開しています。
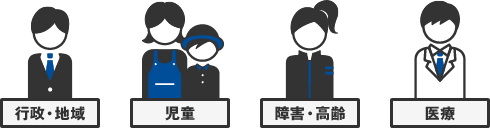
「社会福祉士」は法律上の名称であり、資格の名称がそのまま職種の名称になるとは限りません。
例えば、福祉事務所ではケースワーカー、社会福祉施設では生活相談員、社会福祉協議会では福祉活動専門員、
医療機関では医療ソーシャルワーカー(MSW)、教育機関ではスクールソーシャルワーカー(SSW)などと呼ばれています。
社会福祉士になるには
社会福祉士になるには、厚生労働大臣が指定した指定試験機関である
(公財)社会福祉振興・試験センターが実施する「社会福祉士国家試験」に合格しなくてはなりません。
この国家試験を受験するためには、法律に定められた受験資格が必要です。
受験資格の取得
01
厚生労働大臣が指定する科目を履修し、正科生として卒業する
- (国家試験を受験する年度末に卒業する必要があります)
02
演習・実習科目の単位を修得する
- ※実務経験により、現場実習が免除になる場合があります。
社会福祉士
国家試験を受験
合格
受験資格を取得するには
本学で「社会福祉士国家試験受験資格」を取得するためには、 「01」と「02」の要件を満たす必要があります。
入学年次セルフチェック
【必ずご確認ください】
入学年次セルフチェックは、あなたの学歴をもとに入力された内容から見込み結果を表示するもので、
入学にあたっての正式な決定ではございません。
また、この結果をもって編入学の合否を判定するものではありません。
- ※入学・編入学の可否、入学年次、既修得単位認定数は、出願後の正式な審査を経て確定する為、入学年次セルフチェックの結果と異なる場合がございます。
- ※入学・編入学の資格や既修得単位認定数は2026年度入学の方を対象に試算しています。
- ※高校・専門学校などに在学中の方は、本学ご出願時点での見込み学歴を選択ください。
- ※大学・短期大学の専攻科・別科は編入学年として受け付けることができません。
入学年次セルフチェックは、あなたの学歴をもとに入力された内容から見込み結果を表示するもので、
入学にあたっての正式な決定ではございません。
また、この結果をもって編入学の合否を判定するものではありません。
- ※入学・編入学の可否、入学年次、既修得単位認定数は、出願後の正式な審査を経て確定する為、入学年次セルフチェックの結果と異 なる場合がございます。
- ※入学・編入学の資格や既修得単位認定数は2026年度入学の方を対象に試算しています。
01
厚生労働大臣が指定する科目を履修し、正科生として卒業する
(国家試験を受験する年度末に卒業する必要があります)
要件
124 単位以上
(うちスクーリング単位30単位以上)を修得すること
- ※入学・編入学時に既修得単位認定された単位を含みます。
- ※入学・編入学年によって卒業までに修得が必要な単位数が異なります。
- ※スクーリング30単位には、入学・編入学の既修得単位のうち、スクーリング科目として認定された単位を含みます。
- ※オンデマンド科目で修得した単位は、スクーリング単位として認定されます。
卒業に必要な124単位のうち、「必修科目」「選択必修科目」「社会福祉士指定科目」を修得すること
必修科目
- 福祉経営序論
1単位
- スタートアップセッション
1単位
- 社会福祉士指定科目
48単位
- ※選択必修科目には社会福祉士指定科目が含まれています。
必要年数以上
在学すること
【1年次入学の場合】
入学後4年以上在学
【2年次編入学の場合】
入学後3年以上在学
【3年次編入学の場合】
入学後2年以上在学
【4年次編入学の場合】
入学後2年以上在学
- ※4年次編入学でも2年間必要なカリキュラムです。
02
演習・実習科目を修得する
演習・実習科目とは
社会福祉士の国家試験受験資格を取得するための科目です。実習科目は現場への配属実習が必要となります。
また「テキスト学習」と「スクーリング学習」2つの学習形態を通じて学びます。
テキスト学習は課題レポート等を作成する記述式の学習方法です。科目によって講師の添削指導があります。
社会福祉士の演習・実習科目スクーリングは、全国7都市で開講※。
(演習・実習科目は卒業単位数に含まれません)
※2026年度予定
ソーシャルワーク演習
相談援助の実践をイメージし、概念や技術について学びます。
実習や実践での体験を振り返り、理論と結びつけることによって、専門的な知識や技術の習得を目指します。
科目名
- ソーシャルワーク演習 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
ソーシャルワーク実習指導
相談援助実習の意義、実習施設や実習施設のある地域の理解を深め、実習前年度から学習や実習に向けた手続きを行い、「実習計画書」を作成します。
実習後の指導は、実習体験を振り返り、専門的援助技術を身につけることを目指します。
科目名
- ソーシャルワーク実習指導 Ⅰ・Ⅱ
ソーシャルワーク実習
2箇所の実習施設において32日間かつ240時間の現場配属実習を行います。
実際に社会福祉の現場で実習を行い、相談援助に関する専門知識、専門援助技術および関連知識を学びます。
科目名
- ソーシャルワーク実習
| 社会福祉士 演習・実習科目(新カリキュラム) | |||
|---|---|---|---|
| 科目名 | 開講学年 | 科目形態 | 備考 |
| ソーシャルワーク演習Ⅰ | 3年次 | テキスト学習+スクーリング学習(1日) |
スクーリング開催地 北海道・東京・神奈川・愛知 |
| ソーシャルワーク演習Ⅱ | テキスト学習+スクーリング学習(2日) | ||
| ソーシャルワーク実習指導Ⅰ | テキスト学習+スクーリング学習(1日) | ||
| ソーシャルワーク演習Ⅲ | 4年次 | テキスト学習+スクーリング学習(2日) |
スクーリング開催地 北海道・東京・神奈川・愛知 |
| ソーシャルワーク実習指導Ⅱ | テキスト学習+スクーリング学習(3日) | ||
| ソーシャルワーク実習 | 現場実習 32日間かつ24時間以上 |
実習先は大学が決定します。 |
|
-
※「社会福祉士実習履修者選抜」を実施します(実習免除者は除きます)。詳細につきましては
 出願手続要項にてご確認ください。
出願手続要項にてご確認ください。
- ※実務経験による「ソーシャルワーク実習指導Ⅰ・Ⅱ」、「ソーシャルワーク実習」の免除が可能です。
- ※演習・実習科目の課題の作成および提出にあたってはMicrosoft Wordのソフトウェアが必要です。
- ※実習希望地に対応するスクーリング会場については毎年見直しを行います。2027年度以降変更する場合があります。
演習・実習指導の流れ
テキスト学習
テキストや学習指導書を読み、課題に取り組みます。

演習課題・添削課題
『演習課題』や『添削課題』に取り組みます。課題レポートを作成し、インターネットで提出します。講師の添削指導を受け、合格するまでレポートを繰り返します。
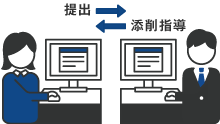
- ※一部添削指導のない課題や郵送での提出となる課題もあります。
スクーリング学習
実習に向けての心構えや、手続き、相談援助のロールプレイ、事例検討などを学びます。スクーリングならではの学習です。
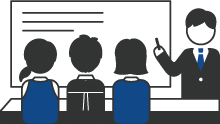
単位認定
所定の課題、スクーリングを修了し単位認定となります。

実習の流れ
実習先の決定
大学が指定する「指定実習施設」から大学が調整し、決定します。

事前訪問
実習先の実習指導者への挨拶、実習内容の確認などを行います。

現場実習
2ヶ所の実習施設において合計32日間(240時間以上)の実習を行います。うち、「ソーシャルワーク実習」(1ケ所目)(4年次以降)を5月~8月に24日間(180時間以上)行い、「ソーシャルワーク実習」(2ケ所目)(4年次以降)を10月~11月に8日間(60時間以上)の現場実習を行います。実習指導者の指導に従って行います。
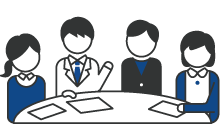
巡回指導
巡回指導教員が実習中に巡回指導を行います。
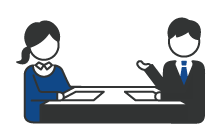
単位認定
所定の時間数、プログラムを修了し単位認定となります。

指定実習施設
実習先は、大学が決定します。
入学後に「社会福祉士実習履修者選抜」
を実施
社会福祉士国家試験受験資格を取得するためには、演習・実習科目を履修しなくてはなりません。
実習科目の履修が必要な方には「社会福祉士実習履修者選抜」を実施します。
詳細は『![]() 出願手続要項』をご確認ください。
出願手続要項』をご確認ください。
※ただし、「実習免除者」は「社会福祉士実習履修者選抜」はありません!
実習免除について
社会福祉士国家試験受験資格の取得を目指す場合、入学時(入学前年度の3月31日まで)に、指定施設で1年以上の
相談援助業務実務経験がある方は実習免除(「ソーシャルワーク実習指導Ⅰ・Ⅱ」「ソーシャルワーク実習」の免除)を受けることができます。
ただし、実習免除を受ける場合でも、演習科目である「ソーシャルワーク演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」は単位修得する必要があります。
実習免除
- ソーシャルワーク実習指導 Ⅰ・Ⅱ
- ソーシャルワーク実習
上記の科目が免除されます。
- ※ただし実習免除を受ける場合でも、演習科目である「ソーシャルワーク演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」は単位修得する必要があります。
学費モデル
養成のポイント
社会福祉士 国家試験受験資格
担当教員インタビュー

上山崎 悦代 准教授
研究分野:社会福祉学
- かみやまさき えつよ:「保健医療と福祉」、「多職種連携の実践(IPW)と多職種連携教育(IPE)の実践」、社会福祉士の資格科目を担当している。
終末期ケアにおける多職種連携のあり方を中心に、連携・協働とソーシャルワークの関係に関する研究に取り組む。
「高度な実践能力」のあるソーシャルワーカーを目指して
福祉経営学部に在籍している学生像は、実に多様です。すでにソーシャルワーカーとして福祉現場に身をおきながら実践している、介護や医療の現場で日々のケアに携わっている、福祉とは全く異なる業種で活躍している、高等学校卒業後に本学部を選択し大学生活を楽しんでいる…等、枚挙にいとまありません。と同時に、社会福祉士の資格取得を目指す学生にとっては、皆同じ「資格取得」を目標とし、そこに向かって一歩ずつ歩みを進めています。
社会福祉士は、さまざまな生活上の困難を抱える人や地域の福祉課題に向き合い、多職種・多機関等と連携・協働しながら、解決に向けて共に歩むソーシャルワーク専門職です。横たわる課題は決して単純ではなく、複雑で難しいものばかりと言えるでしょう。しかし、それを見過ごすことはできません。どのような困難な課題であっても、そこに向き合う意欲と専門性に裏打ちされた知識や技術、そしてその根底にある価値・倫理といったものが、私たち社会福祉士には常に問われています。そして、誰に対しても、何に対しても真摯に謙虚に向き合う姿勢が必要であることは言うまでもありません。その積み重ねの先に、人々や社会からの要請に応えられるソーシャルワーク実践が展開されるはずです。
本学部では「高度な実践能力」のあるソーシャルワーカーを養成しています。そのため、多くの学習、そして、長期間にわたる実習(一部の方は実習免除)に取り組まなくてはなりません。その学ぶべき量は決して少なくないと言えるでしょう。けれども、多様なバックグラウンドを有する学生同士が、持てる知識や経験をベースにしながら、互いの良さを活かして切磋琢磨し、同じ目標に向かって歩んでいます。その豊かな多様性こそが、本学部の強みでもあり、大きな特徴でもあります。
高度な実践能力を獲得する道のりは決して楽ではありませんが、あなたのソーシャルワーク実践を待っている多くの人、地域、社会があるはずです。
高い志と情熱を持って、ぜひ社会福祉士にチャレンジしてください。
国家試験対策講座

国家試験受験対策講座では、忙しい社会人の方でも参加しやすいように様々なプログラムを開講しており、2024年度は延べ3,680名が受講(外部受講生含む)しました。
講座内容としては、1~2日間の短期集中で重要項目や受験テクニックなどを解説する「対面講座」や、学習の習熟度を客観的に確認し復習することで知識の定着を図る「模擬試験」、日常の隙間時間を有効に活用するPCや携帯を使った「WEB講座」などを開講しています。
国家試験に的を絞った効率的な学習コンテンツを提供することで、資格取得を強力にバックアップします。
※対策講座の受講料は学費に含まれておりません。
関連情報
通信教育部の特徴
日本福祉大学 通信教育部が多くの方に選ばれている理由、学びやすさのポイントをご紹介します
学習システム・カリキュラム
充実した在宅学習でのサポートとPCに不慣れな初心者をサポートします
入学・学費案内
本学部の1年間のスケジュールをお知らせいたします
実績データ
在学生・卒業生の声
本学部で学ぶ学生たちの日常。そして卒業してそれぞれの目標に羽ばたく卒業生の横顔がご覧いただけます
願書・資料請求

『出願手続要項』やパンフレットなど、入学に関する詳しい資料請求は、こちらからお申し込みください。
入学説明会日程

日本福祉大学 通信教育部では、全国で説明会を開催しています。
お問い合わせ

日本福祉大学通信教育部へのお問い合わせは、電話、FAX、Eメールにて直接受付させていただきます。