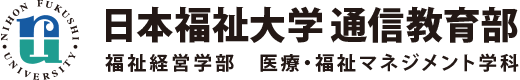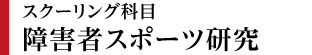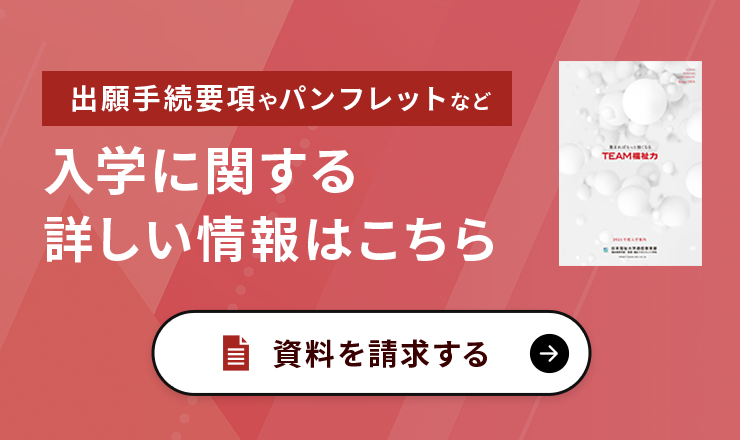ここからページの内容です
お知らせ
本学美浜キャンパスにて、「障害者スポーツ研究」のセッションスクーリング(対面授業)が開催されました。スポーツは、競技性だけではなく、気軽に行い、継続していくことで健康維持・増進、体力の向上につながるものです。その他にも人とつながるためのコミュニケーション手段としても非常に効果的です。障害に合わせてルールや方法を工夫することにより、いろいろなスポーツを行うことができ、障害がある人も、自分は「できる!」という自信を持つことができます。この科目では、障害がある人がスポーツを通じて「生きがい」を感じ、積極的に社会参加を行えるきっかけ作りになることを学びます。
本学通信教育部は、通信制では全国唯一の障害者スポーツ指導者資格取得認定校であり、障害者スポーツの実技を含めたスクーリングは通信制では本学のみが実施しています。本授業は、初級障がい者スポーツ指導員(公益財団法人 日本障がい者スポーツ協会)資格を得るための一環の授業です。
※「初級障がい者スポーツ指導員」の資格を取得するには、今回のスクーリングのほかに、「障害者福祉論」「スポーツマネジメント」の全科目を正科生として単位修得し、「公益財団法人 日本障がい者スポーツ協会」に申請することが必要です。
スクーリングには多様な年齢、職業の方など、約200名の学生が参加しました。今回は本スクーリングのレポートをお届けします。
スポーツを通して、工夫次第で障害者の可能性が広がること、コミュニケーションの手段になることを実技を体験して理解する。
担当教員:荒賀 博志
1.本科目の講義目的と到達目標
【講義目的】
(1)障害者にとってスポーツとは何かを考える
障害がある人こそスポーツを行うべきではないか。スポーツは、競技性だけではなく、気軽に行い、継続していくことで健康維持・増進、体力の向上につながるものである。その他にも人とつながるためのコミュニケーション手段としても非常に効果的である。障害に合わせてルールを変更したり、方法を工夫することにより、いろいろなスポーツを行うことができる。このことから障害がある人も、自分は「できる!」という自信を持つこともできると考える。本科目では、障害がある人がスポーツを通じて「生きがい」を感じ、積極的に社会参加を行えるきっかけ作りを行うことが、障害者スポーツ指導員の役割であることを理解する。
(2)できることを見ていますか
障害があると、どうしてもできないところを見てしまうのでは・・・。障害がある人がスポーツを行うときは、「できるところ」を引き出していく考え方が大切である。スポーツを通じて、障害がある人の可能性を引き出す「できるところ」を見つける目を養うことが、本科目の目的である。
【到達目標】
- 障害者スポーツ指導員の役割を理解できる。
- スポーツを通じて障害がある人の可能性を引き出すことができる。
- スポーツの役割を理解できる。
2.講義の内容
1.障害者スポーツの概要と現況についての講義

2.実技3種目程度体験する
車椅子バスケットボール、ボッチャ、サウンドテーブルテニス(視覚障害者対象の卓球)、フライングディスク、車椅子卓球などから選択

3.グループでの新しいゲーム作り
身近な道具を使って、自分たちの施設でもできる体を動かすゲームを、様々な障害者ができるように工夫して作り上げ、発表をする。

4.具現化するための討論

5.障害者スポーツをテーマにした映画を観て、障害者に対してスポーツとはどんな意味があるかを考える。

6.シンポジウムの開催
障害者スポーツに関わっている当事者やボランティアのゲストを迎え、現状や課題などを話してもらう。

7.障害者や高齢者に対するスポーツの効果についての講義

8.科目修了試験
3.講義の様子
まず、最初は、担当教員による全体講義。障害者スポーツが誕生した経緯や日本の障害者スポーツの現状について理解を深めます。また、障害者がスポ―ツを生活の中で楽しむことができるようにするにはどのようにしたらよいのか、今後の障害者スポーツの課題や将来像について考えます。


導入講義の後は実技を行います。「車椅子バスケットボール」「ボッチャ」「サウンドテーブルテニス(視覚障害者対象の卓球)」「フライングディスク」「車椅子卓球」の中からあらかじめ選択し、事前に配布した日程表にそって行動します。
「車椅子バスケットボール」
基本(ゴールの高さ、コートの広さ、得点など)は一般のバスケットボール(障害のない人のバスケットボール)と同じです。車いすから見上げた、ゴールの高さにみなさん驚いていました。

「ボッチャ」
ボッチャは、ヨーロッパで生まれた重度脳性麻痺者もしくは同程度の四肢重度機能障がい者のために考案されたスポーツで、パラリンピックの正式種目です。ジャックボール(目標球)と呼ばれる白いボールに、赤・青のそれぞれ6球ずつのボールを投げたり、転がしたり、他のボールに当てたりして、いかに近づけるかを競います。


「サウンドテーブルテニス(視覚障害者対象の卓球)、車椅子卓球」
サウンドテーブルテニス(視覚障害者対象の卓球)は、視覚障害のある人にとっては空間でボールを捕らえることが十分にはできないため、一般に行われている卓球とは異なり、「音」を頼りにして台上でボールを転がしネットの下を通して打ち合う競技です。当日はサウンドボールテニスの他にも、車椅子卓球の実技が行われました。




「フライングディスク」
一般的に「フリスビー」という名が知られていますが、「フリスビー」は商標名なので、「フライングディスク」という言葉が総称として使われています。フライングディスクでは、3回投げてどれだけ遠くに投げられるか競う種目「ディスタンス」、標的の輪をめがけ、10回連続投げて通過した回数を競う種目「アキュラシー」など、様々な種目があります。



実技の間には「新しいレクリエーションを考えよう!」をテーマに様々な障害がある人でも身近な道具を使って体を動かす新しいゲーム作りのグループワークや、「スポーツの効果について~当事者、支援者の立場から~」というテーマでのシンポジウム、障害別指導案の作成演習が行われました。
グループワーク「新しいレクリエーションを考えよう!」

シンポジウム「スポーツの効果について~当事者、支援者の立場から~」



本件に関するお問い合わせ
日本福祉大学通信教育部事務室
| 住所 | 〒470-3295 愛知県知多郡美浜町奥田 |
|---|---|
| 電話 | 0569-87-2932 (平日 9:30-17:00) |
| FAX | 0569-87-2308 |
| メール | tsqa@ml.n-fukushi.ac.jp |
願書・資料請求

『出願手続要項』やパンフレットなど、入学に関する詳しい資料請求は、こちらからお申し込みください。
入学説明会日程

日本福祉大学 通信教育部では、全国で説明会を開催しています。
お問い合わせ

日本福祉大学通信教育部へのお問い合わせは、電話、FAX、Eメールにて直接受付させていただきます。