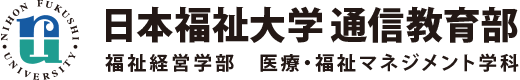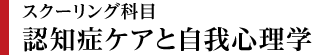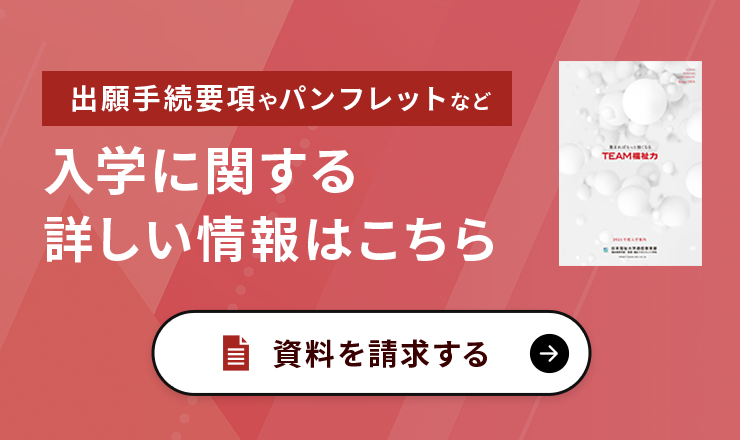ここからページの内容です
お知らせ
セッションスクーリング『認知症ケアと自我心理学』(担当教員:訓覇法子教授)がおこなわれました。認知症は高齢になるほど発症率が高くなるため、認知症ケアは長寿・超高齢社会日本が直面する最も深刻な課題です。認知症ケアの難しさは、認知症疾患とその進行によってパーソナリティの基礎をなす自我機能が悪化・低下することにあり、これらの変化は多様な認知障害(問題行動)の背景となっています。このスクーリングでは、良い認知症ケアとは何かを考え、認知症ケアの基礎をなす、人間を理解するための自我心理学を学びます。スクーリングには多様な年齢、職業の方など、約120名の学生が参加しました。本スクーリングのレポートをお届けします。
認知症ケアの基礎をなす、人間を理解するための自我心理学。
担当教員:訓覇法子教授
1.本科目の講義目的と到達目標
【講義目的】
●良い認知症ケアとは何か
認知症は高齢になるほど発症率が高くなるため、認知症ケアは長寿・超高齢社会日本が直面する最も深刻な課題である。認知症ケアの先進国スウェーデンは、国政基本方針(2010年)において早期医学診断の他、本人中心のケアや複数専門職によるチームワークの必要性とともに、教育の重要性をケアの質向上の重要な条件として掲げる。本人を中心としたケアとは、良い認知症ケアの出発点とは何か? 信頼ある人間関係の形成はなぜ重要なのか? 支援する人のパーソナリティ(人なり、人柄、個人性)を理解することは、ケアの質向上にどのような意義をもたらすのか?教育による知識向上がもたらす意義を考える。
●パーソナリティを構成する自我機能
認知症ケアの難しさは、認知症疾患とその進行によってパーソナリティの基礎をなす自我機能が悪化・低下することにあり、これらの変化は多様な認知障害(問題行動)の背景をなす。認知症の人の尊厳や自己決定を尊重し、できる限り自立した生活を可能にするのが、弱まった自我を支える対応法である。最善のケアを提供するには、まず認知症の人の自我機能の変化を理解し、内包される多様な能力を総合的に把握することが必要である。自我とは、認知、感情、行動などの精神諸機能を統制する心的機関・装置である。実践を根拠あるものにし、良い人間関係を形成するにあたっても、精神的負担の重い介護職員や家族が自らの自我機能を分析することが必要である。支援を必要とする人と支援する人の出発点として、12の自我機能の基礎知識を修得する。
【到達目標】
-
認知症ケアとは何か、質向上のための必要条件、特に教育の重要性を理解することができる。
- 本人を中心とした認知症ケアの出発点とは何か、認知症の人を個々人として理解し、信頼ある人間関係形成の重要性を理解することができる。
- 人間理解や認知障害の背景をなすパーソナリテイの変化を理解し、対応に必要な自我心理学の基礎知識を習得し、説明することができる。

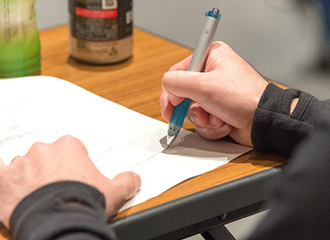
2.講義の内容
1.講義の目的と目標の設定・講義の進め方

2.良い認知症ケアとは何か

3.スウェーデン認知症ケアの基本方針

4.認知症ケアに自我心理学を必要とする理由

5.基礎医学の知識(ゲスト講義)

6.パーソナリティの基礎をなす12の自我機能

7.認知症に起こりやすい障害と対応の仕方
3.講義の様子


初日は、担当教員による全体講義。本人中心のケアや複数専門職によるチームワークの必要性とともに、認知症ケアの質向上のために必要な教育(知識向上)の重要性を学びます。また、最善の認知症ケアとは何か、信頼ある人間関係の形成はなぜ重要なのか? 支援する人のパーソナリティ(人なり、人柄、個人性)を理解することは、ケアの質向上にどのような意義をもたらすのか?教育による知識向上がもたらす意義を考えます。


講義内では、適宜グループワークが行われます。「ケアとは何か?」、「良いケアとは何か?」、「本人を中心としたケアとは何か?」を考え、お互いの意見を交わします。教員の専門性と社会人学生の多様な経験経験の交流が授業を深めます。


グループワークの後は、再び、担当教員による全体講義。なぜ認知症ケアにおいて自我機能に関する自我心理学の知識が必要なのかを考え、さらに自我及び自我機能とは何かを理解し、自我心理学者ベラック(Bellak, 1973)に基づいた12の自我機能とそれらの自我機能の相互作用を学びます。


担当教員の講義終了後は、認知症疾患の専門医によるゲスト講義が開講されました。認知症ケアの重要な前提である認知症疾患に関する医学的な基礎知識と認知症の治療に地域がかかわる必要性について講義されました。


2日目は、自我機能の基礎知識を踏まえて、認知症疾患によって生じる多様な認知障害・自我機能の変化(悪化・低下)を考察し、支援する人が「補助自我」として認知症の人の弱まった自我機能を補助し、支える対応法の具体例を取り上げ、各自の実践や経験に照らし合わせて理解を深め、講義が締めくくられました。
4.教員から一言
 ケアを可能にし、ケアの質を高めるための出発点は、ケアされる人とする人との信頼ある人間関係の形成にあります。どうすれば、相互に満足するケアが可能になるでしょうか?信頼ある人間関係を形成する作業は、誰もが経験してきたように相手の人となりを理解することから始まります。では、漠然とした人となりをどうやって理解すればよいのでしょうか?一つの方法が、それぞれの人となりを作り上げている「心の装置」(自我機能)を理解することです。ケアされる人の人となりだけを理解しても十分ではありません。相手の人となりに答える自分の人となりを知って初めて、双方が満足し、信頼できる人間関係を形成することができます。さらに重要なことは、自分という人間の可能性と限界をきちんと知ることによって、専門職としてケアにおける倫理とは何かを考える一歩を踏み出すことが可能になることです。
ケアを可能にし、ケアの質を高めるための出発点は、ケアされる人とする人との信頼ある人間関係の形成にあります。どうすれば、相互に満足するケアが可能になるでしょうか?信頼ある人間関係を形成する作業は、誰もが経験してきたように相手の人となりを理解することから始まります。では、漠然とした人となりをどうやって理解すればよいのでしょうか?一つの方法が、それぞれの人となりを作り上げている「心の装置」(自我機能)を理解することです。ケアされる人の人となりだけを理解しても十分ではありません。相手の人となりに答える自分の人となりを知って初めて、双方が満足し、信頼できる人間関係を形成することができます。さらに重要なことは、自分という人間の可能性と限界をきちんと知ることによって、専門職としてケアにおける倫理とは何かを考える一歩を踏み出すことが可能になることです。
本件に関するお問い合わせ
日本福祉大学通信教育部事務室
| 住所 | 〒470-3295 愛知県知多郡美浜町奥田 |
|---|---|
| 電話 | 0569-87-2932 (平日 9:30-17:00) |
| FAX | 0569-87-2308 |
| メール | tsqa@ml.n-fukushi.ac.jp |
願書・資料請求

『出願手続要項』やパンフレットなど、入学に関する詳しい資料請求は、こちらからお申し込みください。
入学説明会日程

日本福祉大学 通信教育部では、全国で説明会を開催しています。
お問い合わせ

日本福祉大学通信教育部へのお問い合わせは、電話、FAX、Eメールにて直接受付させていただきます。