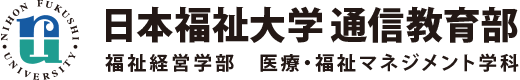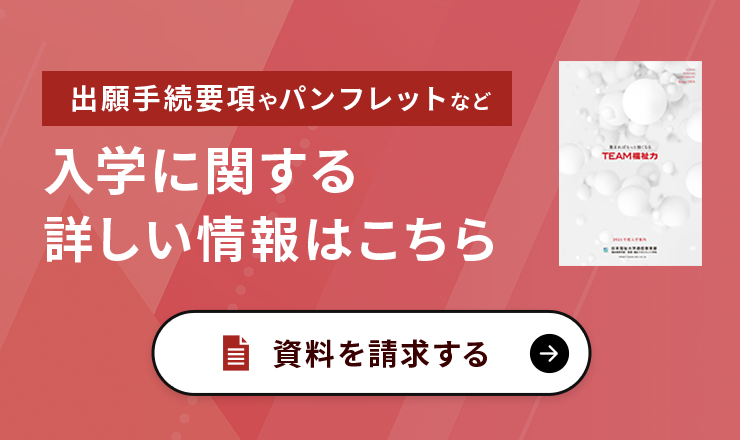ここからページの内容です
お知らせ
「大阪地域学習会 in Tokyo~福祉の源流から潮流を学ぶ~」が開催されました
2015年8月1日(土)、2日(日)の2日間に渡り、都内にある社会福祉法人睦月会及び社会福祉法人 滝乃川学園を学びのフィールドとして、単位認定型の地域学習会が開催されました。
今回の学習会では、福祉経営学部(通信教育)綿先生と元岡先生を担当教員として、都内に拠点を持つ二つの社会福祉法人の現場を訪れ、フィールドワーク、施設見学、ゲスト講師による講義、参加者主体のグループワークといったプログラムよる学習会となりました。関東地域在住だけでなく、中国地域、関西地域といった遠方からの受講者もあり、卒業生・在学生合わせて15名の参加となりました。
【担当教員】
福祉経営学部(通信教育)教授 綿 祐二先生
福祉経営学部(通信教育)学習指導教員 元岡 征志先生
【大阪地域学習会 in Tokyo概要】
2015年8月1日(土)9:30-19:00
| 9:30~9:50 | 社会福祉法人 睦月会へ集合:受付、出欠確認等 |
|---|---|
| 9:50~11:00 | オリエンテーションと資料の配布等 |
| 11:00~13:00 | テーマ:『障碍児療育の現状と課題』 ~障害受容とソーシャルワークの役割について考える~ ゲスト講師(障害児の母親)による講義と現場の見学 |
| 13:00~14:00 | ランチミーティング |
| 15:00~16:30 | テーマ:『カスタマイズ型グループホームの立ち上げについて』 ~ずっと地域で暮らすための生活設計を考える ~ ケアホーム西東京の見学と講義 |
| 16:30~18:00 | グループディスカッションと発表 |
| 18:00~19:00 | まとめの講義と振り返り |
| 19:00~ | 場所を移動して、関東地域の本学在校生らと大交流会 |
2015年8月2日(日)9:30-18:00
| 9:30~9:45 | 社会福祉法人 滝乃川学園に集合:受付、出欠確認 |
|---|---|
| 9:45~10:00 | オリエンテーションと資料の配布等 |
| 10:00~12:00 | テーマ:『支援の源流を学ぶ』~なぜ、福祉が始まったのか~ ゲスト講師:石井亮一、筆子記念館館長 米川 覚氏 |
| 12:00~13:00 | 施設及び記念館の見学(天使のピアノ、墓碑など) |
| 13:00~14:30 | 社会福祉法人 睦月会「わかばの家」に移動後、食事体験と施設見学 |
| 14:30~16:00 | 賑笑工房「てくてく」へ移動後 コーヒー生豆の手選り体験 |
| 16:00~17:00 | テーブルトークと振り返り |
| 17:00~18:00 | まとめの講義、解散 |
今回の地域学習会では、福祉経営学部(通信教育)綿 祐二教授が理事長を務める社会福祉法人睦月会における新たな取り組みと福祉の源流ともいえる滝乃川学園の歴史と変わらない実践に学ぶ有意義な地域学習会となりました。
【地域学習会開催の様子】
≪1日目≫


1日目のゲスト講師のお二人と綿先生


現場の見学風景

バスで移動の様子


交流会の様子
≪2日目≫


滝乃川学園の正門にて


ゲスト講義風景(講師:滝乃川学園 石井亮一・筆子記念館館長 米川氏)


滝乃川学園 石井亮一・筆子記念館『天使のピアノ』(日本最古の輸入ピアノ)前にて

施設での食事を体験


就労作業:コーヒー生豆の手選作業の体験

まとめの講義風景
学習会の最後には、参加者それぞれが学びとったこと、新たに気づいたこととともに、それぞれの実践における課題の解決や新たなチャレンジについてもレポートとしてまとめました。


参加者全員で記念撮
●主催者の声
- 今回の地域学習会は、通信教育部の普段の学習形式とは異なり、施設見学や関東地域の仲間と交流を深めることでき、視野を拡げることになりました。そして何よりも参加された皆様が、ご自身の職場や地域、家庭の中での立ち位置を再確認し、目標や役割など、熱い思いを抱き帰途につくことができました。私もまた、小さな一歩を踏み出すことができました。
このような実りある地域学習会を開催できましたのも、偏に先生方をはじめ、ご多忙の中ご尽力頂きました皆様によるものであると感謝致します。また、このような地域学習会を継続して開催できればと思います。ありがとうございました。
●参加学生の声
- 今まで、テキストや想像でしか理解していなかった障害のある子どもたちの生活やご家族の障害受容に至るまでのプロセス、そして必要な支援について、貴重な学びとなりました。今後の自分の仕事にも活かしていきたいと思います。
- 座学の中ではわからなかったことが、現場を訪れたことで実感できました。多分野におけるチームアプローチや異業種との協働など、今後、ますます重要となれる中で、今回学んだことを実践でも活かしていきたい。
- 「福祉は使ってなんぼ、どんどん実践することが大事。福祉人は、言い訳したり、評論家になってはいけない。必要な支援のあり方は、必ず具現化する」という綿先生のメッセージが非常に心に残りました。
- 今回の地域学習会では、自分の福祉に対する覚悟はどうなのか、福祉の源流を学ぶことで改めて振り返ることができました。日常の仕事においても、利用されている方の人生を最後まで受けるという覚悟で臨んでいる。今後も仕事に、自分に対して自信と誇りが持てるような福祉人として生きていくという覚悟を、再認識できる学習会となりました。
願書・資料請求

『出願手続要項』やパンフレットなど、入学に関する詳しい資料請求は、こちらからお申し込みください。
入学説明会日程

日本福祉大学 通信教育部では、全国で説明会を開催しています。
お問い合わせ

日本福祉大学通信教育部へのお問い合わせは、電話、FAX、Eメールにて直接受付させていただきます。