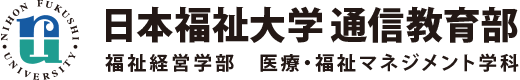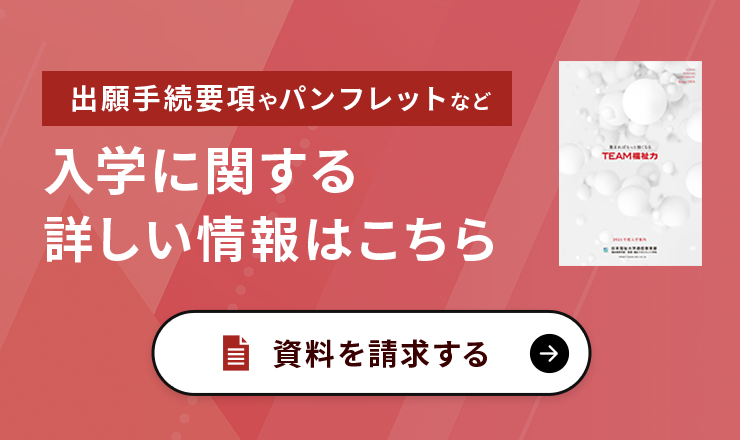ここからページの内容です
お知らせ
「当事者主体の援助と認知行動療法~社会福祉法人浦河べてるの家の実践~」をテーマにした東京地域学習会が開催されました
2013年3月9日、東京都内にあるBumB 東京スポーツ文化館で、地域学習会が開催されました。学習テーマは「べてるの家の非援助論~当事者主体の援助と認知行動療法~」、北海道浦河郡浦河町を拠点とする社会福祉法人浦河べてるの家から、生活サポートセンター長の小林茂さんをゲスト講師としてお招きし、19名の学生(在校生16名、卒業生3名)と2名の本学教員が参加しました。
- 2012年度 日本福祉大学福祉経営学部(通信教育)東京地域学習会
 「べてるの家の非援助論について ~当事者主体の援助と認知行動療法~」のしおり
「べてるの家の非援助論について ~当事者主体の援助と認知行動療法~」のしおり
【本学参加教員】
元岡征志先生<福祉経営学部(通信教育)専任教員>
平澤恵美先生<福祉経営学部(通信教育)専任教員>
●当日のスケジュール
3月9日(土)
| 9:30 | 受付 |
|---|---|
| 10:00~11:00 (60分) |
●オリエンテーションとウォーミングアップ ・朝の気分調べと自己紹介 |
| 11:00~12:00 (60分) |
●講義①「精神障がい者の地域生活支援の現状」 講師:平澤 恵美 先生 |
| 12:00~13:00 (60分) |
●昼食 ・お弁当を食べながらの全体コミュニケーション |
| 13:00~15:00 (120分) |
ゲスト講師: 社会福祉法人浦河べてるの家 生活サポートセンター長 小林 茂 氏 ●講義② 「べてるの家の実践と活動紹介 ~ 今日も、明日も、順調に問題だらけ ~」 |
| 15:10~18:00 (170分) |
●講義③ 「認知行動療法事始め ~自分で自分を助けることのすすめ~」 ●演習ワーク ①幻聴体験ワーク ②ソーシャル・スキルズ・トレーニング(SST) ③リフレーミング ●ゲスト講師への質疑応答 |
| 18:00~18:45 (45分) |
●クールダウンと振り返り(ワールド・カフェ方式) 講師:元岡 征志 先生 |
【地域学習会の様子】
学習会の当日は精神障がい分野だけでなく、様々な領域の支援業務に関わる学生の皆さんが参加されました。オープニングでは、「朝の気分調べ」からスタートし、自己紹介と共に①今日の気分と体調、②最近抱えている苦労、③苦労に対処していること、について参加者全員で共有しました。

オリエンテーションと朝の気分調べ
続く講義では、平澤先生による「精神障がい者の地域生活支援の現状」を導入講義とし、精神障がいに関わる病気の概念や日本における精神保健福祉のこれまでの取り組み、さらには地域における生活支援の状況まで、支援現場におけるさまざまな課題についてわかりやすく解説して頂きました。

平澤先生による講義風景


講師を囲みながらお弁当
午後からは、北海道浦河郡浦河町「社会福祉法人浦河べてるの家」でサービス管理責任者を務める小林茂さんに「べてるの家」の実践をとおして、具体的な支援スキルをベースにした理論的な講義や実践的な演習ワークをしていただきました。自分で自分を助けることを切り口とした「認知行動療法の基本モデル」、実際の現場や職場での支援スキル向上に活用できる「幻聴体験ワーク」や「ソーシャル・スキルズ・トレーニング(SST)」など、参加者全員が時間を忘れたように熱心に取り組んでいました。


ゲスト講師:小林さんの講義風景



演習ワークの様子
学習会の終盤は、1日の講義と演習ワークを振り返るため、ワールド・カフェ方式を取り入れたワークショップで締めくくりました。それぞれの感想や気付きを共有し、学んだことをどのように今後に活かしたいかなど、参加者同士で意見交換をしました。


振り返りとまとめの様子
学習会の終了後には、ゲスト講師の小林さんや平澤先生、元岡先生を囲んで、全員で記念写真を撮りました。また、場所を移動して行われた懇親会では、先生方へのお礼と共に、学習会の事前準備や調整に関わった皆さんの苦労を労い、大いに盛り上がりました。

終了後の集合写真

交流会の様子
●担当教員のコメント
べてるの家に学ぶ「地域学習会」をとおして、精神障がいのある人々に対する支援に、ひたむきに向かい合っている皆さんと、一緒に学ぶことができました。「支援する」ということは、人生を共に歩むなかで生まれる素晴らしい時間だと思います。だからこそ私たちは、真剣に悩んだり、喜んだり、やりがいを感じることができるのだと思います。多くの人々とのかけがえのない出会いを大切に、次の一歩に繋げていきましょう。また、皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。
平澤恵美
今回の地域学習会では、講義による座学に加え、実際の支援現場でも活用できる演習(ソーシャル・スキルズ・トレーニング)やグループワークがふんだんに取り入れられ、お迎えしたゲスト講師の小林さんを囲みながら、非常に充実した学習内容となりました。
開催の当日もさることながら、事前の準備では企画の中心となった志賀さんをはじめ、多くの参加メンバーの協力により、実りある学習会を開催することができました。参加された皆さん、本当にお疲れ様でした。今回の学習会に留まらず、ぜひ、「べてるの家」の活動が実践されている北海道の浦河の地で、さらなる「学び」を共有したいですね。また、皆さんと再会できるときを楽しみにしています!
元岡征志
●企画学生のコメント
精神障がい者の支援員として、日々の現場で直接支援にあたっている中、個人的な葛藤と疑問を抱え苦しい日々を送っていたことが、地域学習会を企画した大きな動機です。今回の学習会では、学習テーマの企画や開催までの事前準備、当日の学びを通じて、様々な領域の支援者である学友達と、多くの問題意識を共有することができました。こうした学習会開催が、学ぶ目的を同じくする仲間との出会いの出発点となって、今後も活発な交流を続けられたら・・・、そしてさらには、関東での継続的な地域学習会の開催ができたら・・・こんなに嬉しいことはありません。
福祉経営学部(通信教育)在校生 志賀志穂
●参加学生のコメント
- べてるの家の活動の原点とも言える「地域の中で自分の仲間と共に自分らしい苦労を取り戻す」、「生きる苦労の主人公になる」という言葉が印象的だった。当事者の苦労に支援者が先回りするのではなく、その人自身の研究課題として向き合うことに支援の本質を学んだ。
- SST(ソーシャル・スキルズ・トレーニング)のワークは、シンプルでありながら理論的、学術的な基盤を背景としている。その理論体系を自分の中に落とし込めていないこともあって、とても難しかった。
- 理念を持って支援することの大切さを学びました。
- 当事者主体であること、援助される側、援助する側ではなく、「一緒にどうしたらよいか考えていこう」と寄り添うことが大切だと思った。「傾聴」は大切だが、「聴き過ぎることは必ずしも良くない」と言う考え方は、目からうろこでした。
- 支援者と支援を受ける人という構造から抜け出し、共に問題を抱えるものとした視線で話すことの大切さを知った。
- リフレーミングを活用して、ネガティブな部分を肯定的な言葉に置き換え伝えることを実践していきたい。
- 相手の良いところを見つけ、ほめるということは、なかなか言葉が出てこないことを実感した。相手の良いところを発見し、伸ばしていくような言葉のかけ方を日頃から意識的に練習したい。
- 専門職のためのSST、PST(プロフェッショナル・スキルズ・トレーニング)という言葉を始めて聞いた。職場のミーティングでも、良い点をお互いに言葉にする練習から取り入れていきたい。
- 今後もSSTについて学び、職員同士で練習しながら職場でもぜひ活用してみたいと思いました。
■本件に関するお問い合わせ
日本福祉大学 通信教育部事務室 地域学習会係
TEL:0569-87-2932
FAX:0569-87-2308
HP:【nfu.jp】-【お問い合わせ】-【通信教育部事務室】
願書・資料請求

『出願手続要項』やパンフレットなど、入学に関する詳しい資料請求は、こちらからお申し込みください。
入学説明会日程

日本福祉大学 通信教育部では、全国で説明会を開催しています。
お問い合わせ

日本福祉大学通信教育部へのお問い合わせは、電話、FAX、Eメールにて直接受付させていただきます。