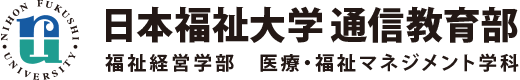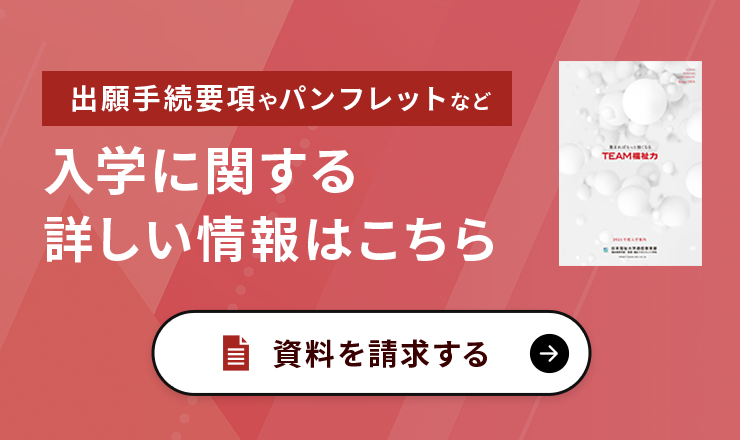ここからページの内容です
お知らせ
不登校やひきこもりについての支援を考える和歌山地域学習会が開催されました
2012年4月29日(日)、和歌山市で不登校やひきこもりについての地域学習会が開催されました。
今回のテーマは「青少年の育ちと支援を考える」でした。
青少年の不登校やひきこもりは、マスコミでも取り上げられ、大きな社会問題となっています。不登校やひきこもりの支援をしている共同作業所「エルシティオ」を訪問し、当事者(メンバー)やスタッフから話を聞くことで、支援の在り方について考えようと、関西在住の10名の学生の皆さんと本学専任教員が和歌山市に集まりました。子育ての経験談も交えながら、充実した学習会となりました。
【本学参加教員】
木村隆夫先生 <福祉経営学部(通信教育)専任教員>
【参加教員のレポート】
現在、若者のひきこもり問題は深刻です。
長期にわたって本人と家族を苦しめています。
今回は、和歌山市のひきこもり支援団体「エルシティオ」を見学し、支援者として活躍されている村山崇之さんと、ひきこもりからの回復途上にある、利用者数名の方から生の声をお聞きすることができました。
「エルシティオ」とは、スペイン語で「居場所」を示す言葉だとのことです。
支援者の村山さんも、ひきこもりの体験者ですが、当事者であったからこそ、苦しんでいる人の気持ちと向き合いながら、心に響く支援ができるのだと感じました。
村山さんの、「しんどくなったら休む、元気になったら働く。エルシティオはそんな居場所です」という言葉が印象的でした。
午後は会場を変えて、「ひきこもり支援のあり方」についてグループ討議を行いました。
まず、「ひきこもりは甘えだ」と考える一部の人が、本人の意思を無視して力ずくで引っ張り出していることについて検討しました。
参加者からは「病気を精神の問題だとして、冬の寒空に放置するようなもの」との意見が出されましたが、村山さんから「ひきこもりはつらい、しかし、その時期に自分とたっぷり向き合えたので今の自分がある」と、ひきこもりも長い人生の中で次のステップにつなげていけるものであることを話されました。
この学習会から、ひきこもり支援者のこころがまえとして、ひきこもり当事者の立場に立ちながら、当事者の「苦しいときは休む、無理はしない、元気を回復したら行動する」という行動を見守りながら、長期的視野に立った支援が大切であることを学ぶことができました。
<福祉経営学部(通信教育)専任教員 木村隆夫>
【和歌山地域学習会 スケジュール(事前・事後課題含む)】
【事前課題の内容】
◎テーマと方法
「ひきこもり支援論」(竹中哲夫著)と「稲の旋律」(旭爪あかね著)の2冊の書籍を読んで感想をレポートにまとめる。
●当日のスケジュール
| 11:00~12:00 |
施設見学 〈施設見学の内容〉 ・参加者、教員、共同作業所「エルシティオ」のスタッフ・メンバーの自己紹介 ・共同作業所「エルシティオ」の活動紹介 ・参加者と教員からスタッフとメンバーへの質疑応答 |
|---|---|
| 12:00~13:30 | 和歌山市駅前レストランでの食事、ホテル会議室へ移動 |
| 13:30~16:40 |
講義とディスカッション 〈講義とディスカッションの内容〉 ・事前課題の2冊の書籍についての発表とディスカッション ・ひきこもりの原因と支援の方法についての講義とディスカッション ・参加者の事例の検討 |
| 16:40~17:15 | 講義 演習 「施設見学と講義、ディスカッションから学んだこと」をまとめ、参加者レポートを作成 |
地域学習会開催の様子
1.NPO法人エルシティオの施設見学(午前)
ひきこもりや不登校の青少年や家族の支援をしている「エルシティオ」のリビング(作業所兼)で、参加者と教員、「エルシティオ」のスタッフである村山崇之さんと4名のメンバーの自己紹介を行うことから始まりました。次に、メンバーが販売用に作業している焙煎されたコーヒーをいただきながら、村山さんから施設の活動の概要を伺いました。最後に、メンバーに作業の達成感、ひきこもりになったきっかけや、エルシティオに通い続けられる理由などを質問して、施設見学を終えました。

【配布されたエルシティオの新聞記事といただいた販売用コーヒー】

【メンバーに熱心に質問する参加者】
2.木村隆夫先生による講義とディスカッション(午後)
事前課題書籍についての発表とディスカッションを行った後、木村先生より、ひきこもりはなぜ起きるのか、また、親や家族はひきこもる人にどのように接したらよいのかなど、ひきこもる人への社会的支援について講義がありました。それを受けて、参加者がそれらについてどう思うか、体験談などを交えながらディスカッションが行われました。最後に、参加者が抱える子どものひきこもりの支援方法を参加者や教員、村山さんと一緒に考えました。

【「エルシティオ」の村山さん(左)と木村先生(右)】

【ディスカッションの様子】
3.最後に
参加された皆さんの感想より
参加後のレポートでは、以下のような感想がありました。ごく一部ですが、ご紹介いたします。
- 人生ゆっくりでよい。そんなに急いで生きていかなくてもよい。(「稲の旋律」の感想)
- 効率を求めようとするこの社会では、どうしてもその環境に合わせられない人たちが出てきてしまいます。この人たちを決して負け組として扱うことのないように社会が変わっていくことを望みます。
- 私自身がひきこもりがちな子を抱え、やはり自らの生き方、いやおうなしに効率化を求められ、その中にどっぷり浸かっている中で、子の気持ちを察することが充分できないことに気づかされ、私自身「中休み」が必要ではないかと反省されられつつも、今後も悩み続けるだろうと思います。
■本件に関するお問い合わせ
日本福祉大学 通信教育部事務室 地域学習会係
TEL:0569-87-2932
FAX:0569-87-2308
HP:【nfu.jp】-【お問い合わせ】-【通信教育部事務室】
願書・資料請求

『出願手続要項』やパンフレットなど、入学に関する詳しい資料請求は、こちらからお申し込みください。
入学説明会日程

日本福祉大学 通信教育部では、全国で説明会を開催しています。
お問い合わせ

日本福祉大学通信教育部へのお問い合わせは、電話、FAX、Eメールにて直接受付させていただきます。