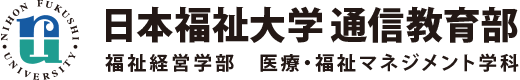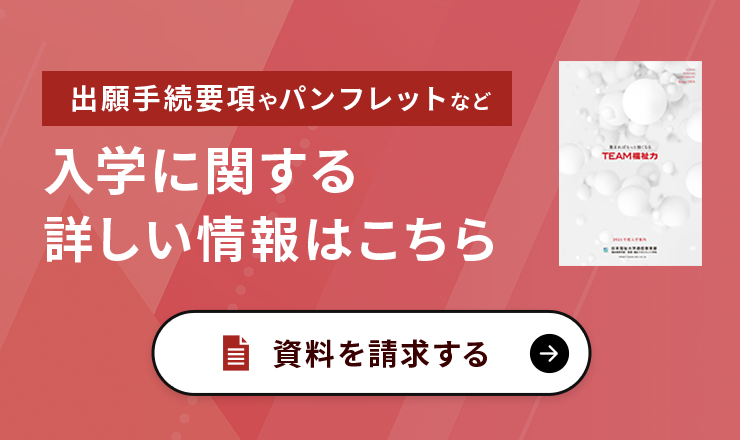ここからページの内容です
お知らせ
相談援助場面における「受容」と「傾聴」の実践をテーマとした大阪地域学習会が開催されました
2012年3月3日(土)、大阪で受容と傾聴を学ぶ地域学習会が開催されました。
今回のテーマは「相談援助場面における『受容』と『傾聴』の実践~『受容』と『傾聴』についての考察~」でした。
対人援助における基本であり、実践上とても重要となる「受容」と「傾聴」について、ロールプレイング等の演習を取り入れながら、「より実践的に理解を深めよう『参加者が各々のもつ価値、倫理について改めて見つめ直してみよう』」と、19名の学生の皆さん(関西11名、東海3名、北陸3名、中国2名)と2名の本学専任教員が参加され、ぎっしりと中身の詰まった学習が進められました。
⇒![]() 【大阪地域学習会のご案内】(学習会当日に配付されたしおりより、一部抜粋)
【大阪地域学習会のご案内】(学習会当日に配付されたしおりより、一部抜粋)
【本学参加教員】
青木聖久先生 <福祉経営学部(通信教育)専任教員>
小松尾京子先生 <福祉経営学部(通信教育)専任教員>
【参加教員のレポート】
対人援助技術の中でも受容と傾聴はとても奥深いものです。受容しているつもり、傾聴できているつもりの実践では、専門的な援助とはいえません。しかし、どのようになったら、受容したといえるのか、傾聴したといえるのか、実はとても難しい問題です。
今回の地域学習会はその「受容と傾聴」をテーマに開催しました。事前課題から受容と傾聴について、苦手意識や「実践できているという実感が持てない」状況が見えてきました。そこで当日は、実践できていると実感を得られるような講義・演習を心がけました。
多くのロールプレイや演習をしましたが、皆さん恥ずかしがることなく積極的に参加していました。それぞれが抱えていた受容と傾聴に関する疑問や課題が少しは解決できたのではないかと思います。また、技術は専門職としての知識・価値に沿ったものであるということも深めることができました。
このように奥深い受容と傾聴ですが、多くの学生のみなさんが関心を持ち、実践できるようになりたいと奮闘している姿に、私自身も多くのことを学ぶことができました。一人でも多くの皆さんが、専門性の高い実践ができることを願っています。
<福祉経営学部(通信教育)専任教員 小松尾京子>
【大阪地域学習会 スケジュール(事前・事後課題含む)】
【事前課題の内容】
◎テーマ
「受容と傾聴について、専門職として大切にしたいことと、実践する際に困難なこと」
◎文字数
特に制限は設けないが、A4サイズで1枚以内
◎注意事項
実践する際に困難なことについては、現場等で経験のある方は、そのことを書いても構いません。全く経験のない方は、実践の場を想定して書いてください。
●当日のスケジュール
| 9:35~10:35 | アイスブレーキング(参加者の自己紹介) 講義 担当:青木先生
〈講義の概要〉・非言語コミュニケーションや対人援助におけるプロセスの大切さについて ・コミュニケーションについて |
|---|---|
| 10:45~12:10 | 講義 事前課題のまとめと考察 演習 担当:小松尾先生
〈講義の概要〉・対人援助における専門性について ・コミュニケーションの重要性について ・位置関係について 等 〈演習内容〉 ・ペアを組んで自分と相手の関係性を捉える |
| 12:20~13:10 | 会場での講師・参加者を交えた食事・休憩 |
| 13:10~15:40 | 講義 演習
担当:小松尾先生
〈講義の概要〉・援助とは何か ・苦しみについて 等 〈演習内容〉 ・会話記録サンプルを基に受容や傾聴についてグループワーク、ロールプレイ |
| 15:50~16:15 | 学習の振り返り 総評 担当:青木先生
|
| 16:15~16:35 | 「地域学習会参加前の私と今の私の変化の有無とその理由」について、 参加者レポートを作成 |
地域学習会開催の様子
1.青木先生による講義・アイスブレーキング(参加者の自己紹介)
青木先生によるアイスブレーキングを活かした自己紹介の発表から始まりました。この中で非言語コミュニケーションの大切さや、対人援助におけるプロセスの大切さを学習しました。

【青木先生によるアイスブレーキングの様子】


【グループごとでの自己紹介発表の様子】
2.小松尾先生による講義・演習(午前の部)
続く小松尾先生の講義・演習では、事前課題のまとめも取り入れながら、「受容」と「傾聴」について、それぞれの意味を掘り下げて考察しました。また、演習では、対人援助における専門性や位置関係について学びました。

【講義・演習を担当された小松尾先生】

【小松尾先生による演習の様子(午前)】
3.小松尾先生による講義・演習(午後の部)
午後に行われた小松尾先生の講義では、主に苦しみの意味や「聴く」ことの大切さ、反復の効果などについて学習しました。演習は、ある実習生と相談者の会話記録サンプルを基に、「受容」と「傾聴」の実践の難しさや「受容と傾聴が成功した状態とはどういう状態を指すのか?」について、グループワークを通じて学習しました。

【小松尾先生による演習の様子(午後)】
4.「インターネット中継」について
今回の大阪地域学習会では、「参加したい!でも遠い。日程の調整がつかない…」という声に応え、地域学習会初の試みとなる「インターネット中継」(※)を行いました。
※一部の講義・演習の様子をWEBカメラで撮影し、インターネット上の動画共有サイトに配信。
およそ10名の学生が視聴され、「当日参加することはできなかったが、学習内容を共有することができた」という感想が寄せられました。
今回は、講義中心の学習会でなく、参加型の演習を中心とした学習会であったため、「インターネット中継」には限界がありましたが、全国に広がる通信教育部のネットワークを想起すると、こうしたインターネットによる中継の活用が今後も望まれるかもしれません。
なお、参加者の中にパソコン・インターネットに長けている学生がおられ、「インターネット中継」を行うにあたってご協力をいただきました。
(以下、「インターネット中継」視聴者より)
- 午前中の内容を視聴しました。とても興味深い内容でした。
- ネット配信に参加させていただきありがとうございます。音声が明瞭で、和やかな学習雰囲気が伝わり、「一緒に学習会に参加してるんだなぁ」と思いました。今回は、皆さんが学習会で学ばれている映像を見せていただきましたが、「次回は直にお会いしたいなぁ」と思いました。
- 内容がとてもよかったです。 「あの場にいたら、緊張してしまうだろうなぁ」とか、できそうで、できてないことを考えながら 視聴させていただきました。

【「インターネット中継」の様子】
5.青木先生による学習会の振り返り・総評
最後に、青木先生より、1日の講義・演習全体を振り返り、総評が行われました。
(以下、青木先生より)
参加者全員の主体性、小松尾先生の授業内容の素晴らしさ、大野先生の側面的支援等が功を奏し、とても素敵な学習会になりました。その学習会から、私自身、4点のことを再認識できました。
1点目は、人を理解することの大切さです。その際、重要なこととして、人は、どのような環境のもと(社会的背景)、どのようなプロセス(歴史)を辿って、「いま・ここにいるか」、ということです。
2点目は、人は誰かに相談をする際、求めているのは、物理的な事実関係もさることながら、気持ちの面で、「今のありのままの自分を受け止めてもらいたい」というものではないか、ということです。
3点目は、支援者は、対象者のことを100%理解することができなくとも、理解しようと努力することができます。また、そのような姿勢が対象者との信頼関係につながるのではないでしょうか。
4点目です。相談援助では、機械ではなく、人が「受容と共感」をすることに意味があります。支援は、テクニックではないのです。「人」ありきであるからこそ、そこには非言語的なコミュニケーションが存在するのだと思います…。
これからも、皆さんのことを応援しています。

【学習会終了後の集合写真】
6.最後に
参加された皆さんの感想より
参加後のレポートでは、以下のような感想がありました。ごく一部ですが、ご紹介いたします。
- 今回の学習会は、実際の相談援助場面を想定した演習が多く取り入れられていた。そのため、参加者一人一人が、机上の学習では得ることが難しかったであろう「受容」や「傾聴」の実践の難しさや、相談者・相談援助者それぞれの価値・感情などについて、実感をもって考察できたとても有意義な学習会となったのではないかと思います。
- 改めて、教科書で書いている「受容」や「傾聴」ではなく、なぜそれが大切なのかが、一つ一つ掘り下げられたと思います。
- (自分の援助や傾聴、受容についての)悩みは100%解決しないだろうが、知識と技術を身につけることで、少しずつ前に進めるのではないかと感じた。
- この学習会で、今後の私と対人に対する距離感が変わる、そんな気がします。
- 相談援助は、相談者である自分の気持ちを出したり、早急にアドバイスや解決策を話しすることではないということを学び、自分がいったい何を不安に思っていたのかを明確にすることができた。
- グループワークを通して自分の価値観であったり、他人の意見を聞くことで、新しい発見が見つかった。
■本件に関するお問い合わせ
日本福祉大学 通信教育部事務室 地域学習会係
TEL:0569-87-2932
FAX:0569-87-2308
HP:【nfu.jp】-【お問い合わせ】-【通信教育部事務室】
願書・資料請求

『出願手続要項』やパンフレットなど、入学に関する詳しい資料請求は、こちらからお申し込みください。
入学説明会日程

日本福祉大学 通信教育部では、全国で説明会を開催しています。
お問い合わせ

日本福祉大学通信教育部へのお問い合わせは、電話、FAX、Eメールにて直接受付させていただきます。