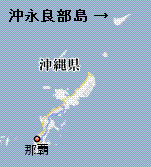2008年3月2日(日)、3日(月)に、鹿児島県・沖永良部島和泊町にて、地域学習会が開催されました。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
 冒頭の概要で紹介されているように、今回は地域包括支援センターに勤務されている本学通信生の「誘致」で実現しました。お仕事柄、地域福祉の研修を希望ということでしたので、その分野の第一人者である平野先生(社会福祉学部)にご多忙中にもかかわらず、協力いただきました。またゲストの久永先生も本学卒業生です。新たに民生委員になられた方と行政担当職員が多く参加されていて、さながら「自ら地域から福祉を生み出していく担い手としての民生委員はどんな活動ができるだろうか」(上からの通達をこなすだけの立場ではなくて)といった実践的な研修になりました。大半の参加者が夜の懇親会にも参加され、思い出深い日となりました。 |
|||||||||||
| 3月2日(日) | |||||||||||
|
|||||||||||
各先生方から、民生委員・児童委員の活動について講義が行われました。 |
|||||||||||
鹿児島女子短期大学 久永繁夫教授 講義:「訪問活動の基本的なあり方について」 |
日本福祉大学 平野隆之教授 講義:「住民リーダーと行政の協働による新しい相談・支援活動について」 |
||||||||||
 |
 |
||||||||||
| 講話終了後、交流会が開かれました。沖永良部島の名物料理と特産品である黒糖焼酎を頂きながら、先生方との活発な意見交換がされていました。交流会は、沖永良部島伝統の踊りで最後を締めくくりました。 | |||||||||||
 |
|||||||||||
| 3月3日(月) | |||||||||||
| ホームページアドレス:http://www.town.wadomari.lg.jp/ |
|||||||||||
| 和泊町役場を訪問しました。昔は小学校の校舎だったそうです。町長の伊地知さんの元を訪れ、島の現状、今後の福祉活動について意見交換を行うことが出来ました。 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
歴史民族資料館を訪問しました。島の写真や昔ながらの道具などが展示され、島の歴史や生活が窺えます。 かつては琉球王国に属しており、現在でも沖縄の『旧正月』を祝うような文化や、方言も沖縄言葉に近く、琉球文化を根強く残していることが分かりました。また、特に目を引いたのは島の特産であるテッポウユリをはじめとしたユリの展示でした。テッポウユリは、100年以上前から栽培をしている歴史の深い花で、現在では全国球根生産量の9割を生産しているそうです。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||